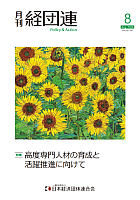経団連は5月29日、定時総会を開催し、新会長に筒井義信・日本生命保険会長を選任、会員企業の代表者ら約300人、オンラインでは150人が出席した。総会では、4人の新副会長を含む新体制を決定するとともに、2025年度事業方針および収支予算を承認した。
月刊 経団連 発刊号一覧
2025年6月号
米国の影響力低下・中国の台頭・米中の戦略的競争の激化、ロシアによるウクライナ侵略をはじめとする国際秩序への挑戦行為、グローバルサウスの台頭などにより国際秩序が大きく揺らぐ中、米国のトランプ政権が矢継ぎ早に打ち出している政策が世界に多大な影響を与えている。

2025年5月号
経団連は、国際的な人材獲得競争が激化していく中で、有為な人材が日本で働くことを選び、活躍できる環境の整備を目的に、外国人政策委員会を設けて活動を展開している。直近では、技能実習制度を発展的に解消させた育成就労制度の創設や特定技能制度の改正、新たな出入国在留管理に関する基本計画の策定などに対し、政府の有識者会議などに参画し、経済界の意見反映に取り組んでいる。
今後の外国人政策のあり方を検討していくにあたり、外国人の受け入れにかかわる多様なステークホルダーとの対話は重要であり、外国人が活躍できる環境の整備に向けた先進事例の共有や機運醸成が不可欠である。

2025年4月号
2025年4月13日に2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開幕する。「いのち」をテーマに、世界の多様な価値観が交流し合い、新たなつながりや創造を促進する場として、未来への希望を世界に示すことが期待されている。

2025年3月号
DXやGXにより加速度的に進展する産業構造の変革や、深刻化する環境問題、地政学的リスクの高まりなど、企業を取り巻く環境は大きくかつ急速に変化している。国内では、少子化に伴う人口減少の加速によって企業環境を取り巻く環境は大きな制約を受けつつある。
こうした中、「デフレからの完全脱却」と付加価値の増大・最大化を通じた「構造的な賃金引上げ」の実現に向けて、2023年と2024年において、多くの企業が約30年ぶりとなる高水準の賃金引上げを2年連続で行った。2025年以降も、この賃金引上げの力強いモメンタムを社会全体に「定着」させるべく、物価動向と「人への投資」の重要性を重視した検討の必要性をより意識しながら、「賃金・処遇決定の大原則」に則り、自社の実情に適した賃金引上げを各企業が積極的に検討し、実施することが求められている。
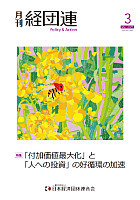
2025年2月号
気候変動問題が厳しさを増す中、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを世界的に加速することが求められている。同時に、国際情勢の不安定化を背景に、エネルギー安全保障・安定供給の確保と現実的なトランジションの重要性が着目されつつある。DX・GXの進展を背景に、今後のわが国の電力需要の見通しが増加に転じる中、国内投資を維持・拡大していくためには、脱炭素電源の導入拡大に向けた道筋の明確化が喫緊の課題である。
こうしたもとで、政府はGX2040ビジョン、第7次エネルギー基本計画、次期NDC(温室効果ガスの排出削減目標)・地球温暖化対策計画を年度内に策定する。
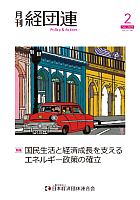
2025年1月号
日本経済は今、歴史的な転換点を迎えている。今こそ30年来のデフレからの完全脱却を実現し、持続的な成長と分配の好循環に資する活動を多面的に展開していかなければならない。そのためには将来の日本のビジョン、目指すべき国家像を示し、様々なステークホルダーが問題意識を共有して、全体最適の視点で取り組む必要がある。
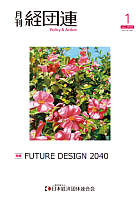
2024年12月号
わが国は激甚化・頻発化する地震や台風・局所的豪雨、新たな感染症など、多くの災害・危機に晒されている。特に大都市圏では甚大な人的・物的被害が想定されるため、政府や地方自治体は様々な災害・危機への対策を強化している。
特に東京都は、首都直下地震や激甚化する風水害などの災害や新型コロナウイルスなどの新たな感染症への対策を重要な政策課題として取り組んでいる。経済界としても、国民の生活を維持し、事業を継続するためには、事業継続計画(Business Continuity Plan)(以下、BCP)の策定を含め、災害や危機に備えることは喫緊の課題であると認識している。
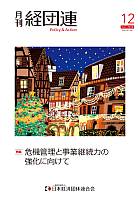
2024年11月号
日本のスタートアップの数と成功のレベルをともに10倍にする目標「10X10X」を官民で共有してからはや2年。政府が打ち出した各種施策がモメンタムを形成し、裾野は拡大しつつある一方、成功レベルの引き上げが課題となっている。
米国などではトップレベルの研究大学からスタートアップが多数輩出され、ユニコーンの半数以上をディープテック系企業が占めている。しかし、日本においては大学研究と社会実装の間にはいまだミッシングリンクがある。 スタートアップを通じた優れた研究の社会実装、すなわち「Science to Startup」こそが、日本のユニコーン増加、そして10X10X実現の鍵である。そこで、日本におけるScience to Startupの実現に向けて、解決すべき課題や取り組みの方向性について議論する。

2024年10月号
複雑化する米中関係やコロナ禍によるサプライチェーンの途絶、軍事転用可能な民生技術(デュアルユース技術)の進化などにより、経済安全保障の重要性が認識され、サプライチェーンの強靭化、機密情報の管理、経済的威圧の抑止などをめぐり、わが国においても法整備や政策検討が行われている。こうした動きは、グローバルなパワーバランスの変化やロシアのウクライナ侵略、中東における紛争により、自由で開かれた国際秩序が不安定化している中で進んでいる。
このような情勢を踏まえ、経団連21世紀政策研究所では、2023年から国際秩序を軸としたプロジェクトを新たに立ち上げ、国別・エリア別のプロジェクトとも連携しつつ、『経済安全保障の地政学』などのセミナーや研究報告を行っている。
急速な人口減少と少子化が進行する中、イノベーションの創出による持続的な成長を実現するためには、多様な人材の強みや個性を発揮できる職場環境の整備が不可欠となっている。
とりわけ、企業における高齢社員の活躍は、わが国で深刻化している労働力問題への対応だけではなく、高齢社員のエンゲージメント向上を通じてパフォーマンスを高めることで、イノベーションを創出し、企業の生産性の向上にもつながる重要な取り組みといえる。
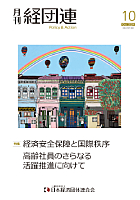
2024年9月号
経団連は7月18、19の両日、軽井沢で夏季フォーラム2024(議長=東原敏昭副会長)を開催した。十倉雅和会長、冨田哲郎審議員会議長をはじめ副会長、審議員会副議長ら総勢38人が参加したほか、国内外から5人の有識者を講師に迎え、「サステイナブルな未来社会のデザイン」を統一テーマに活発に討議した。
フォーラム終盤の特別セッションには、岸田文雄内閣総理大臣が登壇し、「変化を力にする日本」の実現に向けた決意を示した。2日間にわたる討議の成果は、「夏季フォーラム2024軽井沢宣言」として採択され、十倉会長・東原議長が岸田首相に手交した。
2024年は、ブラジルがG20の議長国を務め、ペルーではAPEC首脳会合が開催されるなど、世界の注目が南米に集まる南米イヤーともいうべき年にあたる。
南米は世界最大の日系人社会を有し、長年、日本は鉱物資源や食料などの貿易や多くの日系企業の活動を通じて南米諸国と緊密な関係を築いてきた。経団連も中南米地域委員会をはじめ、ブラジル、コロンビア、ベネズエラの各委員会の活動を通じて、南米諸国との経済関係強化を図ってきた。
本特集では、日本と南米との関係強化の意義に加え、南米に根差して事業を拡大する日本企業の取り組みを紹介する。
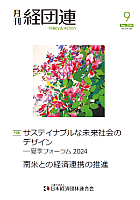
2024年8月号
国際的な人材獲得競争が激化する中、わが国で継続的にイノベーションを起こし、持続的成長を実現していくためには、高度専門人材の育成、獲得、活用が不可欠である。経団連は、会員企業等へのアンケートなども踏まえ、2024年2月に「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」を取りまとめた。加えて、経団連と国公私立大学のトップからなる「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において、博士人材の活躍と大学院教育の充実をテーマに議論を行い、4月に報告書を公表した。