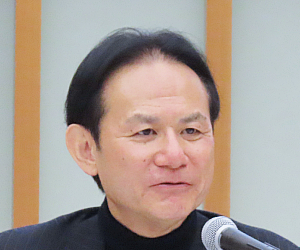
柳氏
経団連は3月21日、金融・資本市場委員会資本市場部会インパクト投融資ワーキング・グループ(宮田千夏子座長)を東京・大手町の経団連会館で開催した。「非財務資本と企業価値をつなぐ『柳モデル』とインパクト加重会計」について、早稲田大学大学院会計研究科の柳良平客員教授から説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ 日本企業の低PBRの原因
近年、日本企業の株価純資産倍率(PBR)の低さが問題視されている。この背景の一つには、日本企業の開示や、投資家との対話が不十分であることなどにより、企業価値の8割以上を占めるといわれる非財務資本が、企業価値評価(株価)に反映されてこなかったことがある。投資家側が、企業の非財務資本を定量化して企業価値算定に織り込むモデルを開発できておらず、伝統的な財務分析等による投資判断を中心に行っていたこともあるだろう。日本企業の勤勉で優秀な人材といった無形の強みが、株式市場ではほとんど「ゼロ」と評価される状況が続いてきたのである。
この状況を説明するのが、私が2000年ごろから検討しているPBR仮説である。国際統合報告評議会(IIRC)が提示する「六つの資本」(注)モデルを基に、PBR1倍の部分は財務資本、1倍を超える部分は五つの非財務資本によって主に構成されると考えている。世界の機関投資家へのアンケートでも、「ESG(環境・社会・ガバナンス)の価値の相当部分は、PBRに織り込まれるべき」との回答が多く、日本企業のPBRが低い一因には、ESGをはじめとした非財務資本が企業価値評価に適切に反映されていないことにもあるといえるだろう。
■ 非財務資本を企業価値につなげる「柳モデル」
非財務資本を定量化しないと伝わらない。そうした思いから開発したのが「柳モデル」である。非財務資本を重要業績評価指標(KPI)として定量的に捉え、それらが中長期的にPBRへ与える影響を実証的に検証した。
19年には、私がCFO(最高財務責任者)を務めていたエーザイのデータを用いて実証分析を行い、モデルを完成させた。モデルでは、例えば女性管理職比率、人件費、研究開発費といったKPI(ESG指標)の増加が、5年後から10年後のPBRを高めるという正の相関を示すことができた。それぞれ金額換算で数百億円から数千億円の価値に相当する可能性がある。
この他、日清食品では、5割程度のESG指標が企業価値を高めていることを示すことができた。これらの結果は、統合報告書やIR活動、さらには投資家との対話にも活用し、海外の投資家からも高い評価を得ている。
■ インパクト加重会計との連携とこれから
海外やアカデミアとの連携も進む。柳モデルは、インパクト加重会計を提唱しているハーバード・ビジネス・スクールのセラフィム教授からも支持を得て、インパクト加重会計の共同研究に発展している。
エーザイでは、人件費の75%に相当する正の雇用インパクト(賃金の質の向上、地域社会への貢献等)を創出していることを示した。この数字は米国の企業の平均を上回る水準である。
日興アセットマネジメントとは、柳モデルでTOPIX全銘柄のデータを分析し、54のESG指標のうち23がPBRと正の相関を持っていることを示した。次のステップは製品のインパクトを可視化することである。
例えばエーザイでは、リンパ系フィラリア症の治療薬が約1900万人に影響を与え、ライフタイムで7兆円、年間1600億円のインパクトを創出したと製品インパクト会計で試算できている。
各社の取り組みの根底には、パーパス(企業理念)がある。柳モデルは企業理念の「暗黙知」を「形式知」化し、統計学的に証明する試みであるといえる。理念を定量化し、企業価値と結び付けて投資家と対話することで、日本企業の評価、すなわちPBRも大きく改善できると信じている。
(注)財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会関係資本、自然資本
【ソーシャル・コミュニケーション本部】


