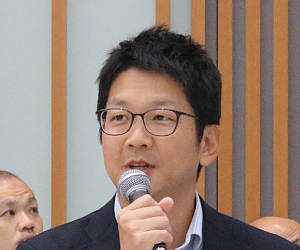
福島氏
経団連は9月19日、東京・大手町の経団連会館で宇宙開発利用推進委員会宇宙利用部会(山品正勝部会長)を開催し、国土交通省大臣官房技術調査課の福島陽介調整官から、国土交通行政の最近の話題や施策の方向性、宇宙・衛星データの利活用事例等について説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ わが国のインフラを取り巻く諸課題
地球温暖化に伴う気候変動の影響で、これまでの常識を超えて、豪雨・台風などの大規模な自然災害が頻発・激甚化し、南海トラフ地震や首都直下型地震などの切迫する巨大地震・津波による甚大な被害の発生も懸念されている。
社会資本の老朽化も深刻化している。高度成長期に整備された道路橋、トンネル、河川管理施設、水道、下水道、港湾施設等のうち、建設後50年を経過する施設の割合が加速度的に高まっており、交通・物流網やライフラインの寸断につながる事案も発生している。
こうしたなか、国交省では、強くしなやかな国民生活を実現するため、防災・減災、国土強靱化の推進のための予算を確保し、インフラ整備等を進めている。
国土強靱化基本法改正により、(1)防災インフラの整備・管理(2)ライフラインの強靱化(3)デジタル等新技術の活用(4)官民連携強化(5)地域防災力の強化――を柱とする「国土強靱化実施中期計画」が策定された。これを踏まえ、国土強靱化を強力に進めていく。
■ インフラメンテナンス・災害対応
老朽化が進むインフラに対し、損傷が拡大してから大規模な修繕を行う「事後保全」ではなく、損傷が軽微な段階で予防的な修繕により機能保持を図る「予防保全」への転換を推進し、「長寿命化」や「トータルコストの縮減」を図っていくことが必要である。
他方で、市区町村では、インフラの維持・管理を担う技術系職員の不足も深刻化しており、効率的な管理のために、デジタル技術等の新技術の活用・導入を促進している。
災害対応については、道路・上下水道、住宅やライフライン等で甚大な被害が発生した令和6年能登半島地震において、合成開口レーダー(SAR)衛星技術等を活用し、土砂災害箇所の早期把握等を行っている。災害対応では、被害状況の把握や迅速な意思決定のため、衛星、ヘリコプター、ドローン等を活用していく。
■ インフラDX、i—Construction、宇宙・衛星データの利活用事例
国交省では、デジタル技術とデータを活用したインフラ分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)を、分野網羅的、組織横断的な取り組みとして進めている。
その中核として、建設現場の生産性向上に向けた「i—Construction 2.0」を推進しており、2040年度までに、省人化3割を目指して自動施工や遠隔施工などの施工のオートメーション化等を推進している。
インフラ分野における宇宙・衛星関連の取り組みとして、衛星測位や衛星データ等の利活用に関し、災害時の被災状況の把握、インフラメンテナスへの活用等を進めている。
具体的には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携した広範囲の浸水や土砂移動の早期把握、ダム貯水池斜面の地滑りやダム堤体変位の監視、海岸線のモニタリングのほか、宇宙建設革新技術開発にも取り組んでいる。
【産業技術本部】


