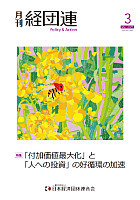2022年に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」において、2030年目標としての「ネイチャーポジティブ」の考え方が示された。
政府は、GBFを踏まえ、「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定し、ネイチャーポジティブ経済への移行を国家目標として掲げるとともに、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」が関係4省により策定された。加えて、政府の成長戦略にはネイチャーポジティブな経済・社会システムへの転換に向けた施策展開と企業の競争力の維持・強化が盛り込まれた。
2026年に開催されるCBD-COP17では、GBFの進捗を評価するグローバルレビューの実施が予定されており、その結果は各国の政策や企業行動に大きな影響を与えることが見込まれている。
こうした中、経団連と経団連自然保護協議会は、グローバルレビュー後の施策展開を見据え、「生物多様性・自然資本保全を新たな成長の源泉とすること」「気候変動対策等との統合的取り組みを促進すること」を掲げた政策提言を取りまとめた。
本特集では、同提言取りまとめの背景とそのポイント、国内外の政策動向や日本企業の動向などを紹介するとともに、ネイチャーポジティブ経済への移行に向けた課題や方策を展望する。
月刊 経団連 発刊号一覧
2026年2月号

2026年1月号
AIの急速な発展・普及、気候変動などの環境変化、紛争激化、格差拡大、社会的な分断の進行、政治の不安定化など、世界経済は複雑化した課題に直面している。

2025年12月号
生産年齢人口が減少し、超高齢社会が進展する中、わが国では健康を維持し、年齢を問わずにより多くの方が活躍できる環境の整備が喫緊の課題となっている。企業は健康経営を通じて、従業員の健康づくりを支援し、組織の活性化や生産性向上、ひいては企業価値向上につなげることが重要である。健康経営が注目されて10年を経て、大企業を中心にその取り組みは定着しつつある。今後は、中小企業や地方におけるより一層の取り組みの深化と裾野の拡大が期待される。

2025年11月号
世界のコンテンツ市場が急成長する中、優れたIPを創出する日本のコンテンツ産業は、目覚ましい成長を遂げている。2023、2024年の経団連提言を嚆矢として、コンテンツ産業は日本の基幹産業と位置付けられ、コンテンツ政策の司令塔として「コンテンツ産業官民協議会」が設置された。官民を挙げた取り組みが進む一方、海外展開目標の達成には、乗り越えるべき課題がいまだ多く残されている。本特集では、座談会、対談、インタビュー等を通じて、現状の課題を掘り下げるとともに、今後のコンテンツ産業のあり方を展望する。

2025年10月号
「地球最後のフロンティア」として高いポテンシャルを秘めるアフリカ。2025年は、大阪・関西万博に45を超すアフリカの国々が公式参加を果たし、8月20日~22日にかけて「第9回アフリカ開発会議(TICAD9)」が横浜で開催されるなど、アフリカへの注目が高まっている。
本特集では、現下の国際情勢におけるアフリカの位置付け、アフリカの社会課題やポテンシャル、アフリカの内発的・持続的な発展に向けて、日本が果たすべき貢献についてを議論するとともに、TICAD9での経団連の取り組みを報告する。
2025年6月に労働施策総合推進法等改正法案が成立し、顧客・取引先からのハラスメント(カスタマーハラスメント)等を防止する措置の実施が企業の義務となる。
職場におけるハラスメントは人権を侵害するあってはならない行為であり、ひとたびハラスメントが発生すれば、被害者や職場に負の影響を及ぼすだけでなく、対応の巧拙が企業のレピュテーションリスクにつながりかねない。企業は、改正法の施行を見据え、ハラスメント防止対策の強化に取り組む必要がある。
本特集では、ハラスメントに関する法制度の概要や改正法への対応策のほか、カスタマーハラスメント防止対策を積極的に推進している企業・団体の事例を紹介する。

2025年9月号
経団連は7月24、25の両日、軽井沢で、「夏季フォーラム2025」(議長=小路明善副会長)を開催した。筒井義信会長、冨田哲郎審議員会議長をはじめ、副会長、審議員会副議長ら計43人が参加したほか、有識者を講師に迎え、「人口減少下でも輝く日本経済・社会の未来図」を統一テーマに活発に議論した。
フォーラム終盤の特別セッションには石破茂内閣総理大臣が登壇し、対米投資促進等を通じた今後の新しい日米関係実現への期待を表明した。経済安全保障・外交、付加価値創出型経済への移行、地方創生、税・財政・社会保障の一体改革等の重要政策の推進にも強い意欲を示した。2日間にわたる討議の成果は「持続的な価値創造が導く日本経済・社会の未来図─経団連夏季フォーラム2025総括」として採択され、筒井会長、小路議長が石破首相に手交した。
世界が対立と分断の色を濃くする中においても、アジアは成長センターとして世界経済を牽引してきており、持続的な成長を実現すべく、さらなる連携・協力が求められている。経団連はこれまでアジア・ビジネス・サミット(ABS)の開催などを通じて、各エコノミーの民間経済団体との交流を推進してきた。
本特集では、ABSの活動報告のほか、アジア開発銀行(ADB)やアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)の動向、日本のインド太平洋戦略にかかわる考察などを紹介する。

2025年8月号
日本のスタートアップの数と成功のレベルを10倍にするという目標「10X10X」。2022年にこの目標を官民で共有して以降、わが国のスタートアップエコシステムをめぐる状況は大きく前進した。裾野(スタートアップの数)は着実に拡大し、大企業にもスタートアップとの連携はイノベーション創出に不可欠、との考え方が浸透しつつある。
本特集では、2025年5月に開催された「経団連 Startup Summit 2025」における討議の模様を紹介するほか、政府の施策動向、地方企業がグローバル展開している事例、大学を中心としたスタートアップエコシステムの最先端の動向などを取り上げる。

2025年7月号
経団連は5月29日、定時総会を開催し、新会長に筒井義信・日本生命保険会長を選任、会員企業の代表者ら約300人、オンラインでは150人が出席した。総会では、4人の新副会長を含む新体制を決定するとともに、2025年度事業方針および収支予算を承認した。

2025年6月号
米国の影響力低下・中国の台頭・米中の戦略的競争の激化、ロシアによるウクライナ侵略をはじめとする国際秩序への挑戦行為、グローバルサウスの台頭などにより国際秩序が大きく揺らぐ中、米国のトランプ政権が矢継ぎ早に打ち出している政策が世界に多大な影響を与えている。

2025年5月号
経団連は、国際的な人材獲得競争が激化していく中で、有為な人材が日本で働くことを選び、活躍できる環境の整備を目的に、外国人政策委員会を設けて活動を展開している。直近では、技能実習制度を発展的に解消させた育成就労制度の創設や特定技能制度の改正、新たな出入国在留管理に関する基本計画の策定などに対し、政府の有識者会議などに参画し、経済界の意見反映に取り組んでいる。
今後の外国人政策のあり方を検討していくにあたり、外国人の受け入れにかかわる多様なステークホルダーとの対話は重要であり、外国人が活躍できる環境の整備に向けた先進事例の共有や機運醸成が不可欠である。

2025年4月号
2025年4月13日に2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開幕する。「いのち」をテーマに、世界の多様な価値観が交流し合い、新たなつながりや創造を促進する場として、未来への希望を世界に示すことが期待されている。

2025年3月号
DXやGXにより加速度的に進展する産業構造の変革や、深刻化する環境問題、地政学的リスクの高まりなど、企業を取り巻く環境は大きくかつ急速に変化している。国内では、少子化に伴う人口減少の加速によって企業環境を取り巻く環境は大きな制約を受けつつある。
こうした中、「デフレからの完全脱却」と付加価値の増大・最大化を通じた「構造的な賃金引上げ」の実現に向けて、2023年と2024年において、多くの企業が約30年ぶりとなる高水準の賃金引上げを2年連続で行った。2025年以降も、この賃金引上げの力強いモメンタムを社会全体に「定着」させるべく、物価動向と「人への投資」の重要性を重視した検討の必要性をより意識しながら、「賃金・処遇決定の大原則」に則り、自社の実情に適した賃金引上げを各企業が積極的に検討し、実施することが求められている。