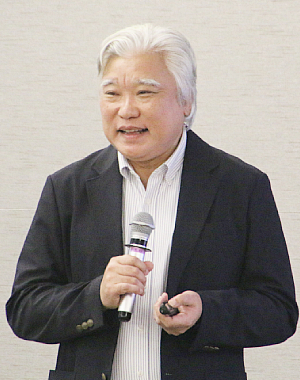
東氏
経団連は9月3日、東京・大手町の経団連会館で観光委員会企画部会(種家純部会長)を開催した。立教大学観光学部の東徹教授から、観光立国の意義、実現可能性、課題等について説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ 政府目標の実現可能性
政府が2016年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」には、20年に訪日外国人旅行者数を4000万人、消費額を8兆円に、30年にはそれぞれを6000万人と15兆円にする目標が掲げられている。
政府がインバウンド誘致に注力するのは、人口減少・少子高齢化に伴い、国内の消費が減少し、経済成長力の衰えが懸念されるため、国内消費の減少分を訪日外国人旅行者の消費で補う必要があると考えるからである。しかし、さらに人口減少が進むと、国内消費の減少をインバウンドで補うことには限界がある。
当面の政府目標を実現するためには、航空座席供給数や空港の受け入れキャパシティなどの拡大が不可欠である。
■ オーバーツーリズムの発生要因と対策
京都の市営バスの混雑や江ノ島電鉄鎌倉高校前駅付近の踏切における交通妨害など、各地でさまざまな問題が生じている。SNSの発達した今日、「映える」写真の投稿が引き金となり、同じ写真を撮ろうとする観光客が特定の場所に集中しており、観光客の想定外の急増に地域が対応できない事態を招いている。
オーバーツーリズムは、過剰な観光需要や好ましくない観光行動・事業活動が地域の観光受容力を超える負荷を与え、住民生活や自然環境、景観等へのネガティブな影響が看過できない程度に及ぶだけでなく、観光客の体験の質および満足度の著しい低下につながる事態である。
観光客は「非日常的」な条件において、「客」の立場で、地域や出会う人との「一時的な関係」を持つことから、自己中心的で享楽主義的な観光行動を取りがちである。SNSの拡散性と扇動性がこれに拍車をかけている。
観光客が訪れる地域に敬意を示さず、地域側もそうした観光客に嫌悪感・反発を抱きはじめる。地域のなかでも、観光からの受益者と不利益を被る者との間の社会的分断を招く危険性もある。
オーバーツーリズムを解決するためには、地域の観光受容力に見合った適正規模の観光を目指す必要がある。
具体的には、(1)需要の分散(2)観光客への注意喚起・警告(3)公的規制、有料化、予約制等による需要の制限・抑制(4)行動の物理的抑止――などの対策が考えられる。
ただし、公的規制は効果が高い分、実現にはハードルが高く、情報提供や啓発は実現が容易だが、実効性を確保するのが難しい。
■ 観光立国の実現に向けた課題
観光立国を実現するためには、地域社会の持続可能性を損なうことのないよう、環境保全の枠組みのなかで、地域の社会的・経済的活力につながる観光のあり方を考える必要がある。そうした理念のもとで、「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりに取り組み、観光産業の「稼ぐ力と働く魅力」を高めていくことが求められる。
観光産業に従事する人材の育成にとどまらず、観光を通じて自然や文化の価値を理解し、地域に敬意を払う意識・態度を身に付け、持続可能な地域社会の実現に向けて取り組んでいく人材を育成することも重要である。
観光客が訪問先の自然・文化・暮らしを尊重し、配慮する態度や行動を取る一方、地域の側も異なるものを寛容に受け入れ、地域の恵みを分かち合う。オーバーツーリズムは、そうした「リスペクト」と「ウェルカム」の関係を失わせつつある。この関係を取り戻し、再構築することが必要である。
【産業政策本部】


