経団連のバイオエコノミー委員会(小坂達朗委員長、岩田圭一委員長)、東京大学と日本パスツール研究所によるPhic(Planetary Health Innovation Center=プラネタリーヘルス・イノベーションセンター)は3月26日、都内で第4回プラネタリーヘルス産学連携イニシアティブ会合を開催した。東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授、同大学院薬学系研究科の後藤由季子教授から、最新の研究内容についてそれぞれ説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ いきモノづくり(竹内氏)
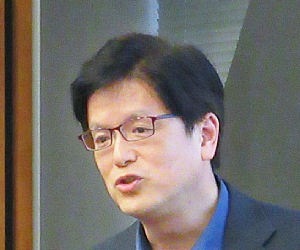
従来、機械系や電気系の研究室では、人工物を使用して世の中を良くする技術の開発が行われてきた。しかし、これだけ技術が発展しても、自然界には人工物では実現困難な機能が多く存在する。例えば、犬は人間の嗅覚を圧倒的に凌駕し、分子のわずかな違いを識別できる。他にも、生きた細胞には自己修復能・増殖能があり、また筋肉や脳はごくわずかなエネルギーで高度な働きができる。
私の研究室では、生物と無生物の「いいとこどり」をすべく、生体材料と工学技術を融合させた「バイオハイブリッドシステム」の開発に取り組んでいる。望みのバイオハイブリッドシステムを作るには、生体機能を構成する各要素の性質や相互作用を理解したうえで、生体材料で構築した点・線・面状の部品を組み合わせ、3次元的に生体組織を再構成することが必要である。当研究室では、2022年には培養ヒト皮膚細胞で覆った自己修復能を持つ指型ロボットの開発、25年2月には世界最大のバイオハイブリッドハンドの開発に成功した。この取り組みから得られた知見は、創薬モデルや新たな治療法の開発にも活用でき、現在、化粧品企業と皮膚をモデル化した研究も行っている。生物と無生物の融合は、どちらか一方だけでは実現できなかった新たなイノベーションをもたらす可能性を秘めている。
また、ウシの筋細胞を培養して食肉を生成する「培養肉」の研究も行っている。培養肉は、食料問題解決や環境負荷低減に寄与する可能性があり、持続可能な食料生産の新たな選択肢として期待されている。現在、シンガポールなどの国で培養肉がすでに販売されているが、それらは培養肉の含有量が非常に低いものである。われわれは本物の肉と遜色ない培養肉の開発に挑戦しており、研究室レベルでは世界最大級の脂肪付きの培養肉の作成に成功している。
■ 大人の脳と子供の脳(後藤氏)

高齢化社会の進展に伴い、認知症の患者数は増加の一途をたどる。認知症などの神経変性疾患は脳にゴミがたまる病気といえ、蓄積したゴミが脳内のニューロン(神経細胞)にダメージを与える。個々の疾患によりゴミの内容と蓄積する場所に違いがある。例えば筋萎縮性側索硬化症(ALS)では、運動制御をつかさどるニューロンが損傷を受けることで手足・呼吸器の運動機能が低下してしまう。ALS患者の皮膚細胞を採取し、iPS細胞(人工多能性幹細胞)化したうえでニューロンへと分化誘導することでニューロンを効率よく作製できれば、ALSの疾患メカニズム解明や治療薬開発につなげることが期待できる。しかし、現状iPS細胞から特定のニューロンへ効率的に分化誘導することは困難である。私の研究室では、この現状を打破したいという思いを持って、ニューロンへの分化誘導に影響する因子を研究している。
また、幼少期のストレスがいかにして脳の発達に影響し、ひいては精神疾患に関係するかについても研究している。マウスを用いた実験では、生後発達期のストレスに脆弱である「臨界期」に社会的孤立等を経験したマウスが、成長後に社会性や認知機能の低下を示すことが知られている。このようなマウスの脳活動ダイナミクスは、人間の自閉スペクトラム症(ASD)当事者の脳活動ダイナミクスと類似していることが分かってきた。これらの研究成果は、人間において幼少期のストレスが脳にどのような痕跡を残すのかを解明する手がかりとなり、将来ASDの早期診断や当事者への行動学的介入に生かせるかもしれない。脳発達の理解を通じて、個々人の個性がポジティブに捉えられ、誰もが暮らしやすい社会づくりにつなげたい。
【産業技術本部】


