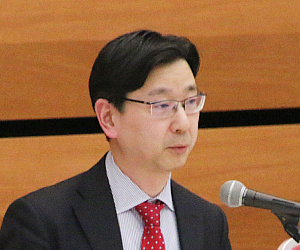
多田氏
経団連は10月10日、東京・大手町の経団連会館で経済財政委員会(柄澤康喜委員長、鈴木伸弥委員長)を開催し、内閣府の多田大臣官房審議官から、令和7年度年次経済財政報告(経済財政白書)および日本経済レポート(2024年度)の関連分析について説明を聴くとともに意見交換を行った。説明の概要は次のとおり。
■ 個人消費の現状と課題
現在、個人消費の回復は力強さを欠く状況が続いている。世帯類型別で見ると、勤労者世帯の消費性向はコロナ禍前の水準に届いていないことが分かる。統計上の技術的なマイナス要因もあるが、純粋な消費意欲の低下が続いている。
消費意欲の低下要因としては、自身の賃金が持続的に伸びるという見通しを消費者が持てていないこと、身近な物品の物価上昇が続き、消費者マインドが低下していること、老後の不安などによって消費を減らして貯蓄に回す動きが起きていること――が考えられる。
総じて、賃金上昇を当たり前のものとして受け止められる環境づくり、安定的な物価上昇率の実現、老後不安を緩和するために社会保障制度の持続可能性を高めていくことなどが政策上重要である。
■ 賃金上昇の実感と持続性
春季労使交渉の結果を見ると、直近2年は定期昇給込みで5%を超える賃金引き上げが実現している一方、賃金引き上げの持続性に関して消費者・労働者はまだ懐疑的である。
この要因を探るために生まれ年別で賃金動向を見ると、いわゆる就職氷河期世代は就職前後に想定していたほどの賃金水準に達していない。そのため今後の賃金上昇の継続性に対しても懐疑的になりやすい可能性がある。
これに加え、物価上昇を割り引いた実質賃金は、1970年代生まれ以降の世代で全体的に、それ以前の世代よりも伸びが鈍くなっている。
こうした状況が、賃金の先行きに労働者が悲観的になる要因となっている可能性がある。
2010年代後半は、人手不足感が強まっていたにもかかわらず、賃金はさほど伸びてこなかった。
各種研究を踏まえるとこの要因は、潜在的な労働力である女性や高齢者の労働参加が進んだこと、賃金水準が相対的に低いパートタイム労働者が増えてきたこと、転職市場が発展途上であったこと、デフレ下で賃金の硬直性が高かったこと――などが考えられる。
ただし、総じて見ればこれらの賃金の伸びを抑制する要因は徐々に解消されてきている。足元で進む賃金上昇の動きを定着させていくことが重要である。
■ 日本とグローバル経済との関わりと企業部門の課題
日本の国際収支は観光と海外子会社からの収益等が黒字、エネルギーやデジタルサービス分野等が赤字である。
世界との関係で見ると、日本は輸入された中間財を加工して輸出する形で、グローバル・サプライチェーンへの参加が進んでいる。
こうしたなか、米国や中国における最終需要の減少による影響を受けやすくなっているともいえる。
日本企業の収益は高水準を維持している一方、企業の資産構成の推移を見ると、資産のうち固定資産が占める割合が下がってきており、大企業では海外投資比率、中小企業では現預金比率が増加しているなど、国内での投資に収益が十分回っていない。規制改革等も通じて、日本での事業環境を改善していく取り組みが必要である。
一方、最近では中小企業で、収益を賃金引き上げや設備投資に割り当てる動きも出てきている。こうした変化をしっかりと捉え、適切に後押ししていく政策が重要といえる。
【経済政策本部】


