経団連は4月16日、「こどもまんなかセミナー」を東京・大手町の経団連会館で開催した。会員企業から89社、約160人が参加し、わが国の人口減少に対する危機意識と若い世代の結婚や出産・子育ての希望をかなえるために社会全体で行動していくことの重要性を共有した。
今号と次号の2回にわたりその内容を紹介する。
■ こども家庭庁からの施策説明
1.三原じゅん子内閣府特命担当大臣(ビデオメッセージ)
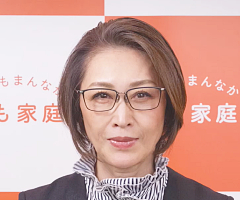
3年目を迎えるこども家庭庁では、発足以来「こどもまんなか社会」の実現に取り組んでいる。未来を担うこどもたちを、社会の真ん中に位置付け、大人がこどもたちの意見を聞きながら寄り添い、支え、こどもたちと共に行動することが重要である。誰一人取り残されることなく健やかにこどもが成長できる社会の実現に向けて、企業には、引き続き、育児休業推進や柔軟な働き方の推進など、子育て世帯を応援する取り組みに協力いただきたい。
2.渡辺由美子こども家庭庁長官

こども家庭庁は「こども未来戦略」を踏まえ、政策を進めている。各種政策を生きたものとするには、何よりも社会全体の構造や意識を変えていくことが重要である。企業には「共育て」の定着に向け、男性育休が当たり前で、育休明けも男女で柔軟な働き方ができる職場環境づくりに引き続き取り組んでいただきたい。また、ケアリーバーなど困難に直面するこども・子育て世帯への支援に当たり、企業との協働への協力をお願いしたい。
■ 有識者からの講演
1.塚越学ファザーリング・ジャパン副代表理事
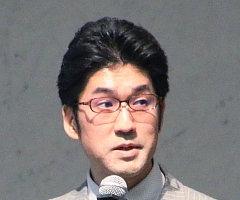
両親だけではなく、行政、地域、職場の同僚や上司、そして企業も子育てのチームメンバーとして社会全体で子育てしていく体制が重要である。単に育休の取得率を上げるのではなく、取得者の希望と、実際の取得方法・時期や取得期間とのギャップを減らし、現場が疲弊せず組織学習力の向上を併せて図ることも必要である。男性育休推進は、職場の業務見直し、効率的業務配分などの組織変革や管理職の行動変容につなげるべきである。「共育て」の第一歩である育休は「ヘルプ」ではなく「シェア」であるべきで、男女ともフェアな育休・柔軟な働き方の実現が不可欠である。
2.小林真緒子氏(東京科学大学大学院生/こども家庭庁「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員)

現在の若い世代は、子育て期も共に働き続ける夫婦像を描いている。こうしたなか、キャリア・結婚・子育てに関して、主体的に向き合えるライフデザイン支援が必要である。自らの価値観や軸を持っている若者ばかりではなく、さまざまな情報が溢れているなか、ライフデザイン支援に当たっては、年代ごとに適切な情報提供と、自分なりの「納得解」を考える機会を提供することが重要である。進路や仕事に関するキャリア教育だけではなく、同時並行で進む、結婚や子育てについて考える機会は特に重要である。こうした機会の提供には、企業も協力できる。
【経済政策本部】


