経団連は3月31日、東京・大手町の経団連会館で資源・エネルギー対策委員会企画部会(武田孝治部会長〈当時〉)を開催した。資源エネルギー庁長官官房の白井俊行国際課長、西村あさひ法律事務所のラース・マーケルト パートナー弁護士から、エネルギー憲章条約(ECT)を軸に、国際エネルギーを巡る動向や投資協定の現状について、それぞれ説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ 白井氏
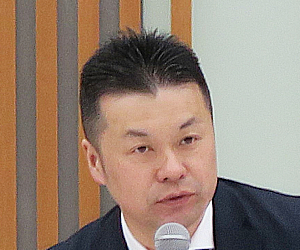
1.ECTの近代化交渉
旧ソ連諸国を中心としたエネルギー投資の保護等を規定する多数国間条約としてECTがある(1998年に発効、日本は2002年)。
発効から20年以上が経過し、各国・地域がカーボンニュートラル(CN)を目指すなかで、条約の内容を近代化するための交渉が行われ、24年12月に改正ECTが採択された。
日本は、多様な道筋を重視し、さまざまな技術への投資を促進する立場からECTの改定交渉に臨んだ。
その結果、水素・アンモニア、バイオ、合成燃料、CCS(二酸化炭素回収・貯留)・CCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)等の分野が新たに保護対象として明記された。一方、EUおよびEU加盟国ならびに英国においては、化石燃料への投資を保護対象とするかどうか選択することとなった。これら締約国においては、改正ECTの発効(締約国の4分の3が批准し、受諾書等を寄託してから90日後)から10年後に既存の化石燃料への投資を保護対象から除外することが規定された。
なお、改正ECTが採択されるまでの間、EUおよびEU加盟国の一部ならびに英国が、ECTから脱退または脱退を表明している。脱退する国は、脱退から20年間、改正前のECTに基づき、化石燃料を含む全ての既存投資を保護する義務を負う。これに対し、EU加盟国のうちECT残留国では、25年9月3日以降に形成された化石燃料投資は、原則として保護対象外となる。
2.G7・G20における議論
日本政府は、経済成長・エネルギー安全保障の確保とともに、各国の事情に応じた多様な道筋・技術によりCNを目指していくことを基本姿勢に、G7やG20等における交渉に参画している。こうした考え方は、23年G7広島サミット以降の成果文書に着実に盛り込まれている。
加えて、G7広島サミットでは、地政学的リスクの高まりも背景に、天然ガスへの投資の適切性について合意文書に盛り込まれた。本合意は、24年のプーリアサミットでも踏襲されている。同サミットでは、石炭火力について、30年代前半または気温上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、われわれのエネルギー・システムから、排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力をフェーズアウトすることに合意した。
■ マーケルト氏

1.エネルギー投資上のリスクと国際投資協定
一般的に、大規模な初期投資を長期的に回収することが求められるエネルギー分野の対外投資には、投資受け入れ国の政策変更に伴う事業・収益への影響や収用、許認可の取り消しをはじめ、複数のリスクが存在する。
企業の投資権益を保護する投資協定では、「実体的保護」として、一般的に、補償なき違法な収用の禁止や公正衡平待遇、内国民待遇等が規定される。また、「手続き的保護」として、企業は国家を相手取り、仲裁の申し立てができる。
2.エネルギー憲章条約近代化への評価
エネルギー分野の投資を保護するECTでも、他の一般的な投資保護協定と同様、投資家による仲裁を含め、広く投資家を保護する規定が盛り込まれている。一方、改定交渉の結果として、投資・投資家の定義、公正衡平待遇の規定が厳格化されたことから、協定違反を認定するハードルが高まる可能性がある。また、改正ECTでは、EU、英国、スイスにおいて、化石燃料投資が保護対象から段階的に除外されることから、欧州に投資する日本企業にも大きな影響がある。さらに、EU加盟国間では、他の加盟国の投資家への投資保護を認めないとしたことも含めて、将来的に欧州以外の他の諸国がこれらを模倣していく恐れもある。
3.日本企業が取るべき方向性
ECTは、日本企業のエネルギー分野の投資を保護する唯一の手段ではない。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)を含め、複数の協定からベストなものを選び、活用することが肝要である。未締結国との投資協定を推進することも重要である。
投資仲裁は時間・コストがかかるが、日本企業にも多くの活用事例があり、有利な判断も得られている。仲裁を申し立てるだけでも、交渉材料(レバレッジ)として、投資受け入れ国との協議を優位に進めることができる。
【環境エネルギー本部】


