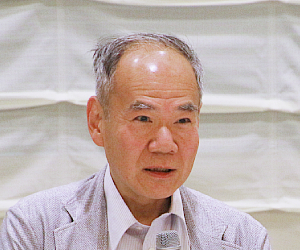
濱口氏
経団連は5月26日、東京・大手町の経団連会館で労働法規委員会国際労働部会(市村彰浩部会長)を開催した。労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口桂一郎労働政策研究所長からプラットフォーム労働に関する政策の動向について、天瀬光二同副所長と渡邊木綿子調査部次長から日本の職場におけるAI活用の実態について、それぞれ説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ プラットフォーム労働に関する政策の動向(濱口氏)
これまでプラットフォームを介する労働を巡っては、労働者保護等の観点から、(1)どのような要件を満たすと雇用関係があると推定するか(2)プラットフォーム上で労働参加を制限・監視するような自動的な意思決定システム(アルゴリズム管理)をどのように規律するか――といったことが欧米を中心に議論されてきた。
例えば欧州各国においては、タクシー配送サービスの運転手や食事配送サービスの配達員が労働者に該当するか否かが裁判で争われてきた。そしてEUは、労働者性の推定とアルゴリズム管理を軸とするプラットフォーム労働指令を2024年11月に公布した。
EUのプラットフォーム労働指令は、プラットフォームと労働遂行者(労働者か自営業者かを問わない)の間に「支配と指揮」を含む要素が見いだされる場合には、雇用関係があると法的に推定する(第5条)。
雇用関係がないと主張する場合の立証責任は、プラットフォーム側にある。自動化された意思決定システムについて労働遂行者は説明を受ける権利を有する(第11条)とある。
EU加盟各国は、同指令に基づき、国内法を26年12月までに整備する必要がある。
こうした動きを踏まえ、25年の国際労働機関(ILO)総会では、プラットフォーム労働に関する条約・勧告案の第1次討議が行われる(別掲記事参照)。
■ 日本の職場におけるAI活用の実態(天瀬氏、渡邊氏)
デジタル技術が急速に発達するなか、人間が担っていた作業をAIが自動処理し、以前にはなかった新しい作業を創出するなど、AI活用への関心が国際的に高まっている。
そこでJILPTは、日本の労働者2万2000人を対象に調査を実施。報告書「AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査(労働者ウェブアンケート)結果」として25年5月に公表した。
同調査の結果によると、勤め先の企業でAIが使用されている人は約13%、自身がAIを利用している人は約8%だった。製造業、金融・保険業のAI利用者はそれぞれ約9%、約18%であり、同業を対象とした22年のOECDの先行研究と比較すると日本のAI利用率は低い。
AIの職場導入時に労働者と雇用主が「対話した」と回答した人は30%以上で、他の新技術使用時(約16%)に比べて多い。対話によって技術導入の効果が高まったと回答した人も、他の技術導入時に比べて多かった。AI利用者のうち、約61%がAIをさらに学びたいと回答したが、実際に学び直した人は約35%にとどまっている。
AIに関する訓練提供や資金援助をする企業の労働者ほど、勤め先の企業が「従業員全体に利益が行き渡る方法でAIを使用している」「AIによる雇用喪失を最小限に抑えようとしている」と回答した人が多かった。
こうした調査結果から、企業はAI導入時に労働者と対話し、学び直しや訓練提供、資金援助を推進することが、AIの効果的な運用に重要といえよう。
【労働法制本部】


