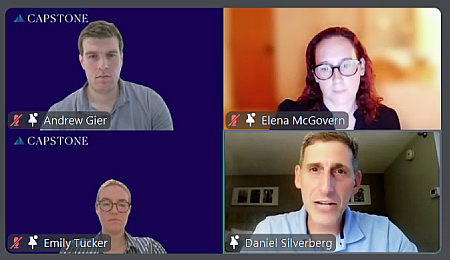
経団連は7月16日、米国の戦略コンサルティング企業であるキャップストーン社のダニエル・シルバーバーグ マネージングディレクター、エレナ・マクガバン マネージングディレクター、アンドリュー・ギア ディレクター、エミリー・タッカー バイスプレジデントを招き、オンライン形式のウェビナーを開催した。トランプ政権の重要政策である外交、エネルギー、通商政策の最新動向について、それぞれ説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ 中東情勢と米国の外交政策(シルバーバーグ氏)
米国は6月、イランの核施設を攻撃し、戦術的には一定の成功を収めた。ターゲットを絞った攻撃により死傷者を出さず、イラン側の反撃も引き出さなかった点は評価できる。
しかし、戦略的成果は乏しい。イランを交渉のテーブルに戻すという米国の狙いは達成できず、制裁解除の見通しも立っていない。イラン経済は混乱しており、日本企業を含む外国企業がイラン市場に再参入できる状況にはない。
イスラエルでは徴兵制を巡り、連立政権を構成する宗教政党とネタニヤフ首相との対立が深まり、政権が崩壊するリスクが高まっている。もし政権が崩壊すれば、中東情勢はさらに混迷を深めるだろう。
■ 米国による関税措置の見通し(ギア氏)
トランプ政権の通商政策は、貿易赤字の削減を最も重視し、関税を交渉手段として利用している。日本に対してもこの点を強調している。米国にとって、対日通商政策は対中戦略の一環でもある。米中間の関税の問題は、次の大統領の政党を問わず、今後も続く可能性が高い。
米国は各国と関税交渉を進めており、現時点(7月16日時点)でベトナム、インドネシアと合意に至っている。中国を包囲すべく、日本を含む他のアジア諸国とも交渉中である。
相互関税の上乗せ部分の一時停止期限である8月1日までに、一時停止期限が延長、もしくは交渉が進展する国が多いと予想している。それでも一部の国は8月1日以降に相互関税率が引き上げられることになる可能性がある。
米国の関税措置には法的な問題を抱えるものもある。相互関税等、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税措置は大統領の権限を越えるとの訴訟が提起されており、動向によっては今後無効になる可能性がある。
もっとも、IEEPAに基づく関税措置が難しい場合でも、関税法338条や通商法122条を根拠にする可能性はある。なお、同301条や通商拡大法232条に基づく関税措置は、法的正当性が比較的高く、今後も継続するだろう。
■ 米国のエネルギー関連の税額控除の動向(タッカー氏)
バイデン政権下で成立したインフレ抑制法によるエネルギー関連の税額控除制度は、減税・歳出法案の成立により大幅に変更となる。この影響は、エネルギー分野ごとに税額控除の廃止時期や特例措置の条件等が異なり、注意が必要である。
【国際経済本部】


