経団連と経団連事業サービス(筒井義信会長)は、経営法曹会議協賛のもと7月10、11の両日、「第127回経団連労働法フォーラム」を開催した(8月7日号既報)。今号では、1日目のテーマ1「有為な人材採用」について川端小織弁護士から、テーマ2「多様な人材活用」について猿木秀和弁護士から、それぞれの報告の概要を紹介する。
■ 有為な人材採用~採用にまつわる法的留意点(川端氏)

新卒の人材獲得競争が年々激化している。まだ新卒一括採用が主流のなか、近年問題視されている「オワハラ(就活終われハラスメント)」の本質や広がりを理解し、対策を講じつつ採用選考を進めることが重要である。内定辞退を防ぐために保護者の内定承諾の同意を強いるなどの「オヤカク(親確)」も、オワハラになり得るため注意が必要である。
学生の約3割が就活セクハラの被害を経験しており、企業側にはOB・OG訪問時のルール整備や社内研修の徹底が重要である。2025年6月には労働施策総合推進法が改正され、「就活セクハラ」の対策が企業の義務となった。
今後、企業が有為な人材を確保していくためには、積極的な情報開示、オワハラへの留意、就活ハラスメントへの対策などが大切である。
■ 多様な人材活用~社員の希望・実情に応じた働き方の提案と課題(猿木氏)
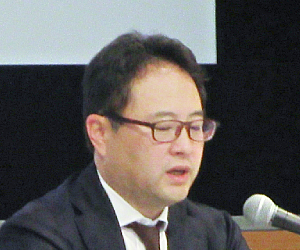
労働力不足が深刻化するなか、従来のメンバーシップ型雇用だけでは、柔軟な働き方や多様な人材の活用が困難になっており、今後は従業員の希望や実情に応じた働き方を提案する必要性が高まっている。
勤務地、職務、勤務時間のいずれかが限定されている限定正社員は、労働者側には希望するキャリア形成の実現、企業側には勤務地・時間に制約のある優秀人材の確保・定着など、双方にメリットがある。
限定正社員を導入するためには、就業規則で各限定正社員を定義する方法だけでなく、既存の就業規則を前提としながら、採用時や限定設定時に変更の範囲を明示して個別契約を結ぶ方法もある。
就労意欲の高い高齢社員の活用は労働力不足対応のカギだが、モチベーションを保ちながら高齢社員に長く活躍してもらうためには、加齢に伴う個人差の拡大や生活観の違いなども踏まえた多様な働き方の提供、定年延長とこれに伴う合理的な報酬制度への変更、65歳超の継続雇用における適切な処遇設計などが企業に求められる。
【労働法制本部】


