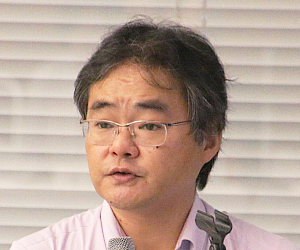
三原氏
経団連は9月2日、東京・大手町の経団連会館で、社会保障委員会医療・介護改革部会(横本美津子部会長)および人口問題委員会企画部会(手島恒明部会長)の合同会合を開催した。ニッセイ基礎研究所の三原岳上席研究員が、2040年に向けた介護や医療の提供体制の改革の論点などを中心に講演した。概要は次のとおり。
■ 40年を見据えた介護・医療の提供体制改革
人材不足が深刻化していくなか、介護サービス提供体制の確保が課題となっている。厚生労働省は「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会を設置し、考え方を取りまとめた。
そのポイントは、今後のサービス需要の変化に応じて、地域を三つの類型に分けて課題や対応の方向性を示した点にある。特に「中山間・人口減少地域」では、サービス維持・確保のための柔軟な対応として、介護報酬体系の見直しや、自治体の役割の強化、事業者間の連携の必要性などが提起されている。
この地域では例えば、サービス体制を確保するため、福祉と介護という異なる分野にまたがって、施設や人材などの資源を有効活用していく必要性が示されている。介護報酬体系もこれまでのサービス提供の「回数」をベースとした出来高払いでは事業者の存続が難しいため、地域の人口に応じた包括払いを中心とする方向性も示されている。
医療においては、医師偏在対策として「重点医師偏在対策支援区域」を設定し、地域に資源を集中投入する方向性を打ち出している。また40年を見据えた「新たな地域医療構想」の報告書では、特に人口減少が進む地域では効率的、効果的に在宅医療などを提供するため、「集住」を促す方向性も盛り込まれた。
総務省の検討会では介護保険など市町村の事務を広域化していくことも提唱された。いずれも大事な論点である。
一方で包括払いには過小サービスという弊害が想定される。広域化に関しても、対人支援業務は住民の身近な部分に残す工夫が必要であり、提供体制と自治体改革の両面で大胆な取り組みをしなければ、人口減少地域でのサービスは維持できない。
■ 介護職員の処遇改善の論点
介護職員と全産業平均の賃金格差は24年時点で6万~8万円程度となっている。インフレ下で人件費や物件費が上がっており、介護報酬の引き上げは喫緊の課題である。
厚労省は24年度の介護報酬改定で訪問介護の報酬を引き下げたが、これは失敗だと認識している。「基本報酬」を下げつつ、「処遇改善加算」は引き上げたものの、処遇改善加算は人件費以外に充当できず、物価高に対応できない。処遇改善加算だけでは限界があり、基本報酬を含めた対応を検討すべきである。
介護現場における生産性向上も重要である。介護報酬上、生産性が向上した場合の人員配置基準の緩和を試行的に実施している。方向性は妥当と考えるが、将来的には人員基準の緩和により、「人材不足問題の解決」と「介護の質の低下リスク」のトレードオフに直面する。
■ 給付抑制議論の行方
少子化対策の財源を捻出するために最大2兆円の歳出改革が必要となる。政府の「改革工程」に基づく高額療養費の見直しが頓挫し、高齢者の自己負担の見直しが有力な方策と考えるが、反対も多く簡単ではない。
自由民主党、公明党、日本維新の会の3党が合意している病床再編の加速、OTC類似薬の見直しなどが論点になる。また、経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)に基づき、政府は今後、歳出抑制努力を継続しつつ、処遇改善を進めるという難しい対応を求められる。
少子化対策の財源を歳出改革で賄う方向性は難しくなったのではないか。
【経済政策本部】


