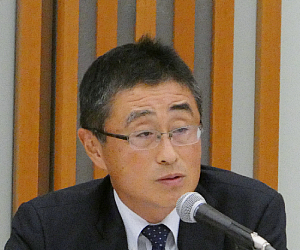
渡邊氏
経団連は9月26日、東京・大手町の経団連会館で通商政策委員会(兵頭誠之委員長、吉田憲一郎委員長、磯野裕之委員長)を開催した。外務省経済局の渡邊滋審議官から「『自由で開かれた国際秩序の維持・強化』に向けたマルチ・プルリ・バイの取り組み状況やWTO改革の動向等」について説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ WTO改革を巡る課題
多角的貿易体制を推進する世界貿易機関(WTO)は、最近では米国の関税措置もあり、その機能低下が指摘されている。2026年3月に開催予定の第14回閣僚会議の主要なアジェンダ候補として、WTO改革が挙げられている。
改革に向けて三つの課題がある。
第一は意思決定の改善である。166の加盟国・地域が全会一致で決定するコンセンサス方式では合意形成が難しく、これまでに成立した協定は貿易円滑化協定と漁業補助金協定に限られる。このため現在、電子商取引協定や投資円滑化協定といった有志国でのルール作りが行われるなど、WTO協定として発効させるための努力が続けられているが、反対国があり実現していない。
第二は途上国地位問題である。韓国、シンガポール、コスタリカは「現在交渉中および将来の交渉において特別待遇を求めない」と表明しており、25年9月には中国も同様の立場を示した。ただし、既存のWTO協定上の途上国待遇まで放棄すると言っていない点に留意が必要である。
第三は紛争解決制度改革である。上級委員会は機能停止に陥っているが、日本も参加する多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA)の拡大が注目される。
■ プルリ(複数国間)・バイ(二国間)の取り組み
日本の貿易総額の約8割はすでに経済連携協定(EPA)等によりカバーされており、これに交渉中の相手国を含めると85%以上に達する。
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)は、市場アクセスおよびルールの両面で高水準の内容を規定しており、締約国の拡大はこれを世界に広げていく意義がある。
24年12月には英国の加入議定書が発効しており、中国、台湾、エクアドル、コスタリカなどがすでに加入を要請している。新たに加入するエコノミーは高い水準を守ることが必要条件となる。
地域的な包括的経済連携(RCEP)協定は、日本の貿易総額の約5割を占める地域との経済連携協定である。香港、スリランカ、チリ、バングラデシュが加入を模索している。
バイのEPA等については、24年8月に日インドネシアEPA改正議定書に署名し、日本の国会で承認済みである。
バングラデシュ、湾岸協力会議(GCC)、アラブ首長国連邦(UAE)などとも交渉を進めている。メルコスール(南米南部共同市場)やアフリカとのEPA等は未締結である。今後も新規交渉の立ち上げの可能性を検討していく。
WTO改革やプルリ・バイの取り組み等により、自由で公正なルールに基づく国際経済秩序を維持・強化し、日本経済の成長につなげることが重要である。
【国際経済本部】


