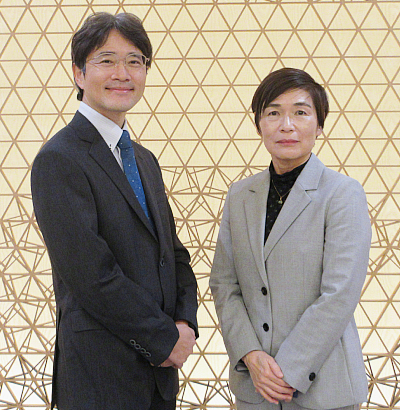
板倉氏(左)と田中部会長
経団連は10月24日、東京・大手町の経団連会館でイノベーション委員会企画部会(田中朗子部会長)を開催した。文部科学省研究振興局の板倉寛学術研究推進課長ならびに学術調査官(科研費担当)(注)である立教大学の橋本栄莉教授、東京科学大学の児島千恵教授、東京大学の藤井壮太教授から、わが国のアカデミアに所属する研究者にとって最も重要な競争的研究費である科学研究費助成事業(科研費)と研究者を取り巻く研究環境について、説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ 日本の研究力の現状
わが国の論文総数の国際的な順位は低下傾向にある。とりわけ引用数が高く、注目度が高いトップ10%補正論文数は足元で13位と、より鮮明に下落している。トップ10%論文は特許に結び付きやすく、イノベーション競争力の低下をもたらす可能性があるため、研究基盤の強化は急務である。
わが国は、他の論文に引用されやすい国際共著論文数が少なく、国際的に注目を集める研究領域でも、参画領域の少なさに加え、新興領域より既存の成熟領域での研究が相対的に多い傾向が見られる。
■ 科研費の役割と成果
わが国の研究力は、国立大学運営費交付金等の基盤的経費(使途や目的の制限がなく自由度が高い予算)と、科研費等の競争的資金によるデュアルサポートシステムで支えられている。
科研費は、毎年約10万件の新規応募のなかから約2.6万件が採択されており、研究の多様性と裾野の広がりの確保、新たなイノベーションの芽の創出に貢献している。
実際、わが国のトップ10%補正論文数の約6割に科研費が関与しており、他の予算・制度と比べても、効率よくトップ10%論文を生み出している。
採択課題の研究内容や成果に関する情報は、科学研究費助成事業データベース「KAKEN」で100万件以上を公表している。ネットワーク構築、産学連携や成果の実用化につなげることが期待され、経済界の方にも積極的な活用をお願いしたい。
■ 若手支援と産学連携強化の重要性
ノーベル賞を受賞した国内大学を拠点とする日本人研究者の全員が、若い頃から科研費による支援を受けてきた。
これを踏まえると、今後、わが国の研究力をさらに高めていくためには、基盤的な研究を引き続き支援することに加え、長期にわたって若手研究者を中心とする既存の学問体系にとらわれない挑戦的・創発的な研究や国際ネットワークへの参入を支援することが重要である。
近年、指摘されている「科学とビジネスの近接化」のように、イノベーションにおける科学の重要性が従来に増して高まっていることに鑑みれば、アカデミアと経済界との間でイノベーションを持続的に生み出す好循環を形成することは不可欠である。
アカデミアと経済界の双方の強みを生かした関係を構築するため、引き続き連携を深めたい。
(注)科研費の審査・評価、制度等の調査や必要な助言等を行う非常勤の国家公務員(大学教授・准教授等と併任)
https://kaken.nii.ac.jp/
【産業技術本部】


